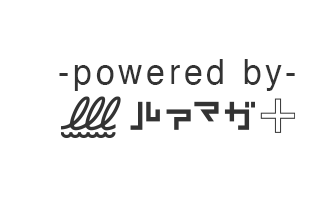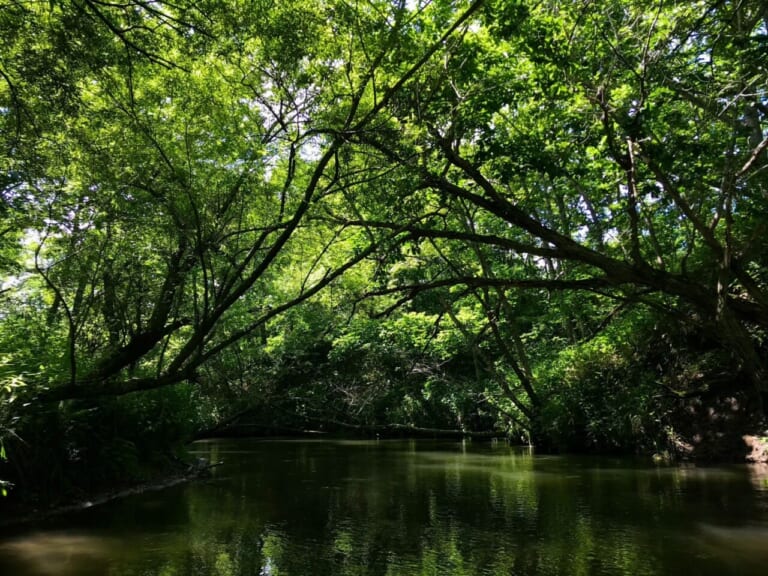暖かくなり、すっかり春となった今日この頃。ハイキングや登山などを楽しむにはピッタリな季節だが、冬眠から目覚めた動物たちが活発的に動き始めるのも春の特徴だろう。今回は、北海道の釣り人が体験した野生動物にまつわる怖い話をご紹介。山や森に行く前にはぜひ読んでおいてほしい内容だ。
●写真/文:小川 貴恵(エクストリーム)
道東の釣り人『佐々木 大』さんにお話しを伺う
3月になり、気温が上がり少しずつ雪解けが進んで来たので、イワナを釣りに川に通い始めた北海道の小川です。
さて、前回まで数回にわたって「見逃しがちなヒグマのサイン」という記事で痕跡などのお話をさせていただきましたが、今回からはヒグマ対策やフィールドの状況などについて、北海道の他の地域で釣りや野生動物に関わる方達から聞かせていただいたことをお話していこうと思います。
前回の記事はコチラ
今回は、釧路在住で、道東をメインフィールドとして釣りをされている、佐々木大さんから伺ったお話について書いていこうと思います。
私は佐々木さんの野生動物や自然、そして釣りとの向き合い方に共感していて、学ぶことも多く、以前からお話をさせていただく機会が何度かありました。ヒグマや野生動物についての記事を書く上で、北海道は広く(函館→釧路間は約540キロも離れています。東京→大阪、もしくは東京→岩手県の距離といえば伝わるでしょうか)地域性もあると思い、ご協力していただきました。
今回お話を伺った佐々木さん。道東の地で渓流釣りなどを楽しむ釣り人だ。
自然豊かな道東の釣り人が考えるヒグマ対策とは?
最初に佐々木さんに「道南と道東では気候や地形などを含めた自然環境がかなり違いますが、どんなところに気を付けてヒグマと遭遇しないように対策されていますか?」と尋ねてみました。
佐々木「私はヒグマの食性に興味を持っていて、釣りに出かけた時も、痕跡には注意しています。例えば春なら、ミズバショウ、イラクサ、フキを食べているのではないか?と思われる痕跡。あとは昆虫類やキノコ類なども食べているような痕跡を川辺で見ることがあるので、それにも気を付けていますね。そのほか秋になると道東では海から川へ産卵のために戻って来たサクラマス、カラフトマス、サケなどを狙いに川原周辺に居つくヒグマが多いと思うのでそれにも注意して行動しています。ヒグマが食べているものに興味を持ち、フンや足跡、食痕と思われる痕跡などをそれに紐づけることで、その季節のヒグマの多いエリアを推測し、遭遇率を低くすることが出来るのではないかと考えています。とはいえ、釣り場である川は水分と食べ物両方を得られる場所だからヒグマに遭遇する可能性は常にあり、注意は怠れません」
ヒグマが土の中の虫などを食べるために掘り返したと思われる跡。
季節ごとの食性について頷きながら話をきいていると、道東の人ならではの視点があることに気づきました。それは「川でサケ・マスを狙うヒグマ」についてです。
ヒグマの食性と地域性
おそらくですが、多くの方は「ヒグマ」と聞くとサケを咥えているところなどを想像すると思いますが、本来ヒグマの食性は植物質を中心とする雑食性といわれています。私の住む道南(渡島半島)では産卵後のサケを他の動物が食べた痕跡は見た事がありますが、私自身、実際にヒグマがサケを食べている姿、食べた痕跡(フンを含め)を見た事はありません。
サケが遡上する河川などで「もしかしたらサケを食べているかも?」という話に、たまになることがありますが、実際のところはどうなのかわかりませんし、むしろ私にとって秋は「ヒグマが山の実り(ドングリやコクワ(サルナシ)やヤマブドウ)を食べに動きまわるからバッタリ出くわさないように気を付けなければならない季節」という考えでした。
「川でサケ・マスを狙うヒグマ」について私なりに考えたことは、よくヒグマに関する報道で「ドングリが豊作、不作」という言葉を聞いたことがあると思います。これはヒグマは雑食性だといわれており、ドングリが豊作か不作かで行動が変化することがあると考えられるからです。
そのような中でヒグマは一度味を覚えると固執するといわれています。道東地域においては、過去を鑑みても、ヒグマがサケ・マスを食べやすい環境があり、味を覚えたヒグマがサケ・マスを食べに川や海に降りてくる傾向にあるのかも知れないと思いました。
これが私の思う道東のヒグマの地域性であり、秋の道東河川ではヒグマと遭遇する危険性が他の地域よりも高い傾向にあると思いました。
ヒグマとバッタリ!を防ぐために
その他にも佐々木さんは「夏は草木が生い茂る分、見通しが悪い場所があったり、風が強い日や川の流れる音で、私たちの存在がかき消されたりすることもあると思うので、ヒグマにバッタリと遭遇しないためにも爆竹や笛などを使用して自分たちの存在を知らせつつ、ヒグマの痕跡にも注意して釣行をしていますね。」とお話していました。
草木が生い茂る夏は、クマの接近に気づきにくいことも。
私は以前、湿原河川に2回ほど遠征したことがありますが、ヨシ(葦)の高さに驚き、そして湿地帯なので足場も不安定なところもあって、独特だと感じました。あと、私が普段行く河川よりも平野部であるにも関わらず、とにかく見通しが悪く風の影響を受けやすい、確かにそんな印象がありました。
変わりゆく時代とヒグマとの距離感
続けて佐々木さんは「近年、”最近ヒグマが増えたんじゃないか?”と思うような感覚が何となく道東の人たちにもありますね。足跡などわかりやすい痕跡を高い頻度で見つけるようになったし、釣り人同士で話をした時に”ヒグマを見かけた”とか、”対岸にいるヒグマに付きまとわれた”という話も聞かれるようになりましたし、私も遭遇したり見かけたりすることが増えました。今では釣りをする上でヒグマに遭遇する可能性は常にあると思って、以前より一層警戒するようになっています。ほかの釣り人を見てもクマスプレーを携行されている方が増えてきましたね。」とお話してくれました。
見かける頻度が多くなってきたヒグマの足跡。
これは北海道全体に言えることで【ヒグマの出没状況は今までとは違う】という事は共通認識のようです。「今まで大丈夫だったから」という考え方では通用しないのかもしれません。今は「以前とは状況が違う」ということを頭に入れて、正しく恐れ、対策を怠らないことが重要ではないかと私は思っています。(実際に北海道のホームページにもヒグマの個体数が増加傾向であると推定されているデータもあります。それに伴い北海道ヒグマ管理計画などの改定や行政も対策等に動き出しているので詳しく知りたい方は北海道のホームページをご覧ください。)
佐々木さんが体験した野犬の怖い話
そして佐々木さんからは「こっちでは野犬が群れでいるんですよね」というお話も伺いました。道東といえば「エゾシカの群れ」かな?と思っていましたが、「野犬が群れで」という言葉には驚きました。
私はその時、頭の中で、昔流行っていた「狂暴な人食いグマに立ち向かう犬たちの漫画」の犬たちが浮かび、思わず佐々木さんに「野犬の群れというと、あの漫画のような想像しかできないんですけど…。」と聞いてしまいました。
佐々木さんは「本当にそんなイメージです。結構前から野犬は見た事がありましたし聞いてもいました。私が初めて見たのはエゾシカを追いかけている犬でしたね。でも野犬なのか、猟犬なのかその場ではどちらかわかりませんでした。それからしばらくして、実際に自分も何度か遭遇したんです。一番怖かったのは何か遠くで犬の鳴き声がするなぁと思っていたら、ガサガサと近づいてきて、最初は警戒した様子の野犬が2頭、3頭がまるで偵察隊のように近づいて来て吠えてくる。後ろの方を見るとポジションが決まっているかのように数頭いて、数えてみたら9頭の群れでした。その時は、とにかくゆっくりと後ずさりしながらどうにか退避しましたが、あれはさすがに怖かったですね。」と真剣な口調でお話しされていました。
実際に道東では野犬による牛への被害が出ており、報道もされていました。ですが、まさか釣り人が野犬に遭遇することがあるとは思いもせず、驚きました。
遠征先の状況を出来るだけ調べることが、身を守ることに繋がる
いろいろお話を聞いてみて、以前、私の記事に書きましたが、北海道庁や市町村のホームページなどを事前に調べておく必要性があることが改めてわかりました。このお話を聞いた後に、野犬について調べてみると釧路市やその他、近隣の市町村でもホームページに記載されていました。
北海道は自然豊かな景色を見ながら釣りが出来る素晴らしいところです。ですが、時に自然の中で生きる野生動物たちが、私たち人間に野生の厳しさをぶつけてくることもあり得ます。ですから釣り人の皆様には、危険な目に遭わないように遠征先の地域について情報を収集し、知識を身につけ、出来るだけしっかりと対策をするようにして欲しいと私は願っています。
そして、もしも釣りや移動時に違和感を感じたら何よりもまず第一に身を守るための行動をとることをお勧めします。次回は別の方に野生動物やヒグマについてまた違う角度からお話しを伺ったので、そのことについてお話して行こうと思います。
山に行くならクマ対策グッズは必須!
小川 貴恵(おがわ・たかえ)
北海道出身、北海道在住の、TULALAフィールドスタッフ。釣り好きの父からの影響で、子供の頃からイワナ、ヤマメ、鮭釣りなどを始める。そのうち、自然と渓流魚の美しさに惹かれ、渓流トラウトをメインに狙うようになる。道内のトラウトフィッシングには精通しており、ルアーフィッシングを始め、フライフィッシングも行う多彩なアングラー。
※本記事は”ルアーマガジンリバー”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。