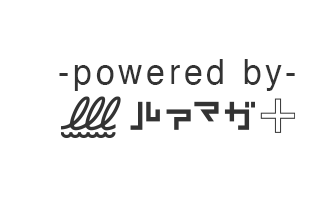クマをはじめとする野生動物の出没が増加している近年。地域によっては熊出没警報が発令されることもあり、緊張感は増すばかり。そんな中でクマによる事故を防ぐためのアイテムが登場。さっそく、北海道で活動する渓流釣りのプロフェッショナル、小川貴恵さんが威力や使い方を試してくれた。
●文/写真:小川貴恵
クマの出没もハイシーズン?
6月になりヒグマや他の野生動物の出没が毎日のように報じられ「人間も野生動物もハイシーズンだなぁ」と感じる、北海道の小川です。
さて、今回は最近発売になった国産クマ撃退スプレー「熊一目散」を購入し実際に噴射して感じたことや、クマ撃退スプレー(以下、クマスプレー)についてお話していこうと思います。
クマスプレーの購入をお考えの方の参考になれば幸いです。
国産クマスプレー「熊一目散」を購入
手にしてみて、まず驚いたのは形状です。輸入品のトリガータイプとは違い、キャップの付いたヘアスプレータイプになっています。初めての形状だったので、釣行に携行する前に熊一目散を装備して噴射態勢に入るまでの一連の動作を確認しました。(どのタイプのクマスプレーでもまずは装備場所と動作の確認をすることをお勧めします)
従来のクマスプレーとは違い、ヘアスプレータイプの熊一目散。
ヘアスプレータイプは初めての形状で噴射イメージがあまりつかなく「噴射の勢いとかどんな感じだろう?」と気になりはじめました。トリガータイプのクマスプレーは処分する時に何度も噴射をしているので噴射圧や液体の色なども理解しています。さらにいうとクマスプレーの威力(刺激や痛みとつらさなど)を誤射や処分時に経験済みです。
以上の経験などを含め、熊一目散を実際に噴射して確認してみようと思い、ある程度のリスクなども考慮した上でフィールドで噴射テストをしてみる事にしました。
噴射テストをした時の状況
山間の渓流で実際に釣りに行く場所であり、ヒグマの出没の可能性のあるエリアで、私が過去に何度かヒグマに遭遇しクマスプレーを構えた時と同じ装備(渓流ロッド、ランディングネット、ウェーダー、ベスト一体型リュック、帽子、偏光グラス、フェイスマスク、グローブなど)をして、入念に風向きを確認しテストを行いました。
この日、風は2~3mありましたが川に入ると周りの木々のおかげでだいぶ風は弱まるのでもう少し弱いと考えて良いと思います。
屋外であり、渓流域での噴射テストなので突然風向きが変わり多少浴びることは覚悟のうえで挑みました。
実際に熊一目散を装備し噴射してみて感じたこと、思ったこと
ヘアスプレータイプでキャップがセキュリティストッパーの役割をしており、専用ホルダーを使用することによってバックルを外しキャップを上に引き上げるとカバーとキャップが同時に外れるので噴射態勢に入るまでの一連の動作がとてもスムーズであると感じました。
専用ホルダーを使用するとカバーとキャップが同時に外れ、緊急時でもスムーズな使用が可能に。
トリガータイプだとセキュリティーストッパーにてこずる事がありますが熊一目散だとそういうことはありません。私は腰に縦方向に装備して噴射しましたが対象方向(ヒグマや野生動物、蠢く茂みなど)から目を逸らさずに取り出し噴射までしっかりできました。これはトリガータイプだと何年訓練しても難しいポイントだったので驚きました。
セキュリティストッパーがついたトリガータイプ。
この「クマから目を逸らさずに取り出す」という動作はなかなか難しく、苦労する動作ですがここが簡単に出来るという所はとても重要なポイントです。初めてクマスプレーを購入する方や、ご年配の方には熊一目散をお勧めしたい大きい理由の一つです。
熊一目散は扱いやすく、片手でも簡単に取り出せますが、それは訓練を重ねてからにした方がいいと私は考えています。いざヒグマ等の野生動物や怪しく蠢く草木を目の前にして噴射態勢に入るときは動揺し焦りがちになると思います。
実際に私はヒグマとの遭遇時、動揺して手の震えが止まらなくなった経験があります。そうなると取り出す際にクマスプレーを落としてしまったり、ミスをしてしまったりすることがあるので、私は取り出しから噴射までの動作は出来るだけ慎重に両手で行うようにしています。熊一目散は両手で扱ってもトリガータイプよりも噴射までの動作は早くかなりスムーズです。
小川さんが遭遇したヒグマ。電柱横の茶色い塊がヒグマだが、写真のような草木に覆われた状況だとお互いの発見が遅れ、バッタリと出会ってしまうことも。
実際に噴射してみて
そして噴射時、私は両手でしっかりと保持して噴射をしましたが、予想よりも噴射圧が強く、噴射し始めの時に噴射圧の強さでほんの少しだけ噴射軌道にブレが生じました。
この点について一般の女性よりも力がある私でもこのような状況になる事があるので、女性やご年配の方などが噴射する際は両手でしっかりと保持し人差し指に力を入れて噴射ボタンを思い切り強く押して噴射するようにした方がいいと思います。
あと、これはあくまで個人的な感想ですが専用ホルダーの取り付けはバックルサイズを選ぶことがあると感じました。釣り人専用の商品ではないため腰に装備する場合、ウェーダーベルトのバックルサイズが大きいものだとベルトに縦方向で専用ホルダーを装備しにくい場合があります。(熊一目散の専用ホルダーは縦、横装備が出来るようになっています)
あと、これからの夏場はウェットウェーディングをする方も多くなると思いますので腰に縦方向に装備する場合は道具用ベルトやカラビナを使って装着するようにするなど、自分なりにカスタマイズするといいと思います。
そしてクマスプレーの威力についてですが、実は噴射テスト時に噴射を終えてクマスプレーをしまおうとした時に急に風向きが変わり、霧状になった熊一目散を見事に浴びてきました。久しぶりの刺激を味わう事にも成功したとても充実した噴射テストでした(笑)。
細心の注意を払い、完全装備をして多少浴びる覚悟はしていましたが、涙と咳が止まらなくなり、さすがカプサイシン2パーセント以上含有されている商品だな……と身をもって実感しました。
ふわーっと霧状になっていて微量しか浴びていないはずでしたが、せき込みや苦しさに私はその場に座り込んでしまい落ち着くのを待ちました。その後、翌日まで口や目元がヒリヒリしていました。
開発者に直接きいてみた。開発決断の経緯
近年、輸入品のクマスプレーの価格が高騰し、国産クマスプレーがあればいいなと私の周りの釣り人の間でも話をすることがあったタイミングで販売になった熊一目散ですが、一体どういう形で開発を始めたのか、バイオ科学株式会社の奥谷さんに実際にお話を伺ってみました。
従来の輸入品であるクマスプレー(左)と国産初のクマスプレー「熊一目散」(右)。
開発を決断した経緯について伺ってみると奥谷さんは
「当社で食品唐辛子を扱っていた事とバイオ科学の仕事の動物、趣味のアウトドアが重なって開発を始めるきっかけとなりました。その際にクマスプレーに国産がない事、為替などの影響で高価になっている事、アーバンベアなど熊による事故などが増えつつある事、事故を起こした熊は駆除されてしまうことなどから、安価で効果的なスプレーを作る事で、人も守り熊も守りながらこの問題を解決できないか、そして誰にでも使いやすく今まで持っていなかった方達(老若男女)に持っていだだける良い物となる事を前提に開発してまいりました。私の力だけではなく、ほかにもいろいろな方々の協力があって出来上がった商品です。」 とお話してくださいました。
実際にアウトドアの遊びをしていると身に迫る危険を感じることもありますし、備えに対して考えさせられることがあるものです。その経験と会社の技術や多方面からの協力によって開発が進み何度も改良を重ねて誕生した熊一目散はまさしく「現場の声から生まれた商品」なのではないか?と私は釣り人やアウトドアを楽しむ人たちの気持ちが届いたような、そんなとても嬉しい気持ちになりました。
「備えあっても憂いあり」クマスプレーを携行しても油断はしない
熊一目散は実際に携行したり、噴射テストをしてみて改めてお勧めしたいと思うクマスプレーですが、以前の記事にも書きましたが「クマスプレーも購入したし、これでもう一安心」ではありません。ヒグマ対策においては「遭遇しないこと、クマスプレーを使う状況にならないこと」が一番なのです。
クマスプレーを使うような状況にならないことが一番。
ヒグマの生息域に入り、釣りや登山をするのであれば、まずは不意な遭遇を避けるための対策(ホイッスルやクマ鈴など)をすることが大切です。
その上で、ヒグマと遭遇した時にクマスプレーは命を懸けた最終防衛手段(攻撃を受けた際の最終防衛手段はナイフやクマナタ、そして防御姿勢)に入る前に、遭遇時にある程度の距離を保ちながら攻撃を回避出来る可能性のあるものです。
決して持っていれば絶対安心できるというものではないという事を頭に入れてクマスプレーを携行して釣りや登山などのアウトドアをしていただきたいと思っています。
今までずっと輸入品のクマスプレーを使用していた方は扱い方に慣れている商品を携行する方がいいと思います。ですが、もしも輸入品のクマスプレーの価格高騰を理由に慣れたもの以外は使えないとクマスプレーの装備自体をやめるということは考えないで欲しいと思っています。
その点、国産クマスプレーは比較的安価で、輸入品と違い為替の動きで価格が大きく変動するものではありません。そしてクマスプレーについて「高い、使いにくい」という考えから持っていなかった方やこれから初めて購入をしようとしている方にも「比較的扱いやすく購入しやすい価格のクマスプレーがある」と熊一目散はお勧めできます。
「自分にできるヒグマ対策」を考えた時に少しでも自分の命を守れる可能性を高める装備としてクマスプレーの携行を続けて欲しいし、新たにクマスプレーを携行する人も今後増えてくれたらいいなと願っています。
それではまた次の記事でお会いしましょう。
小川 貴恵(おがわ・たかえ)
北海道出身、北海道在住の、TULALAフィールドスタッフ。釣り好きの父からの影響で、子供の頃からイワナ、ヤマメ、鮭釣りなどを始める。そのうち、自然と渓流魚の美しさに惹かれ、渓流トラウトをメインに狙うようになる。道内のトラウトフィッシングには精通しており、ルアーフィッシングを始め、フライフィッシングも行う多彩なアングラー。
※本記事は”ルアーマガジンリバー”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。