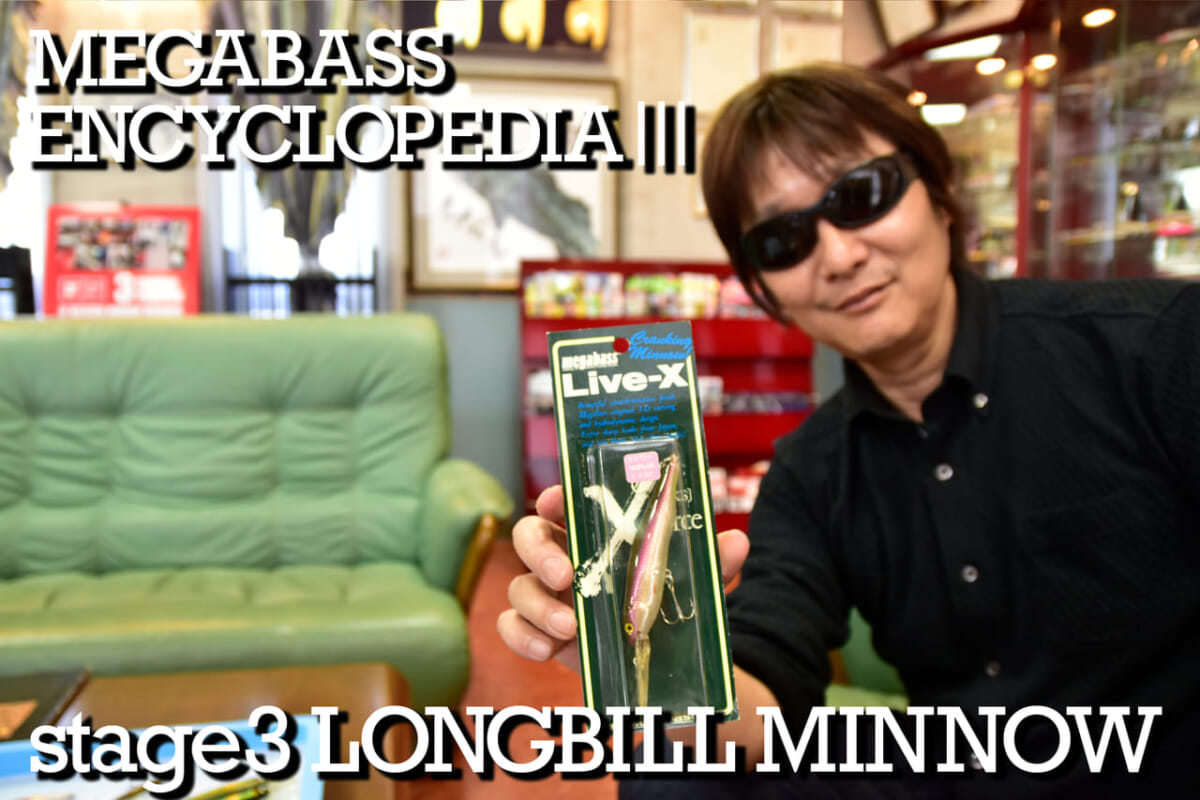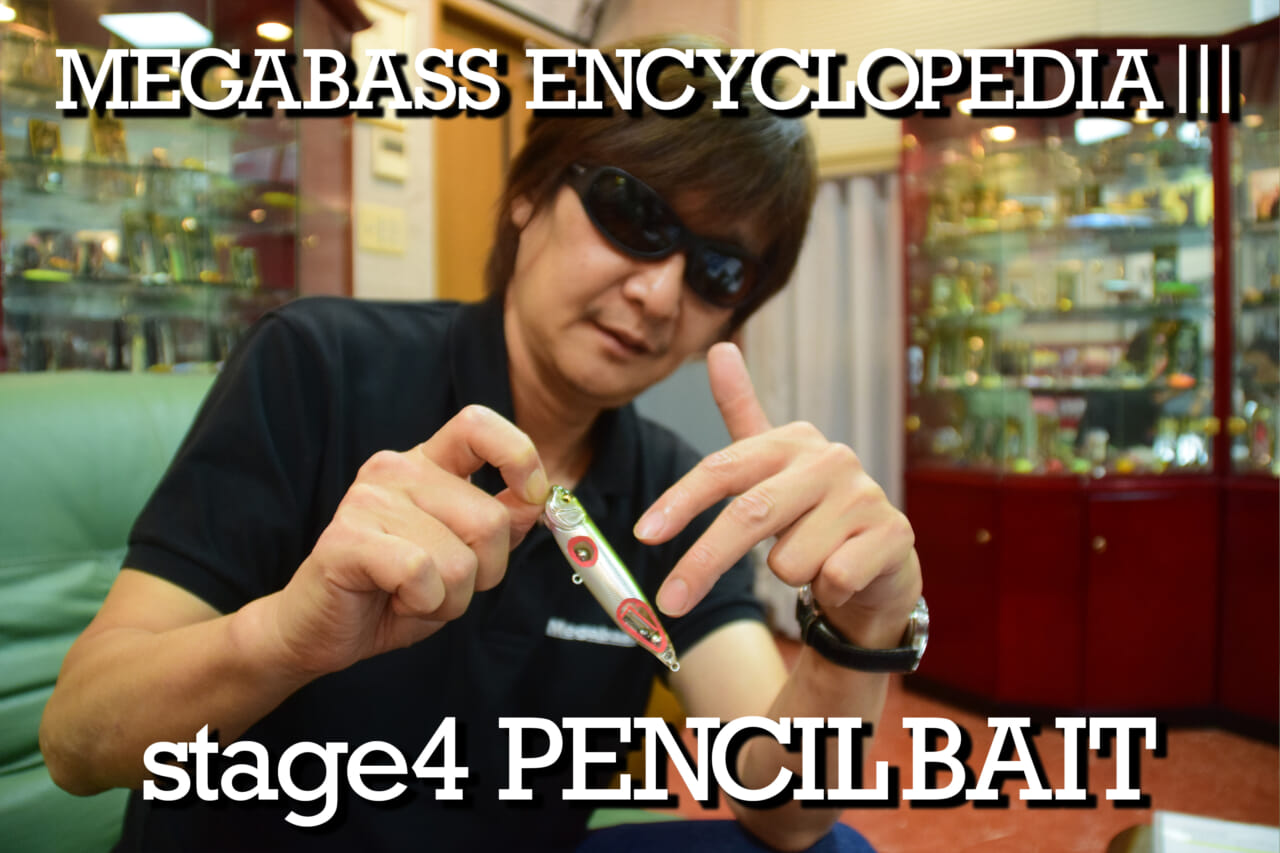創業以来、30年以上にわたりルアーフィッシング業界の最先端を走り続けるメガバス。自社製造を行うルアーメーカーとしては国内外有数の歴史を誇り、その蓄積されたノウハウも世界随一。そんなメガバス&アイティオーグループを一代にして築き上げた社長であり、デザイナーであり、アングラーでもある伊東由樹さんに、メガバス製品が釣れる仕組みや理論、名作ルアーの誕生秘話や歴史など、様々なことを語っていただく大型連載です。
●文:ルアマガプラス編集部
伊東由樹
いとう・ゆき/メガバスを創業し、名作中の名作ルアーをいくつも生み出した天才デザイナー。(財)ジャパングッドデザインアワードでは、200作品を超えるアワード受賞作品をプロデュースするフィッシング/スポーツ用品カテゴリー最多受賞デザイナー。国際的に最も権威と歴史あるIFデザインアワードやレッドドットデザインアワードの受賞歴も持つ。漁師町に育つことで体得した「魚を捕る」ことへの深い造詣が融合するアイテムはどれも時代の最先端であり伝統的。もちろん、アングラーとしての腕前も超一流。
時代を推し進めた新たな重心移動の誕生
38年の歴史を持つメガバス製プラグの歴史は1987年発売のZクランクまで遡る。
そしてこのZクランクの系譜は、2006年の『Zクランク』シリーズ、2009年の『ZクランクX』シリーズを経て、2020年発売の最新作『スーパーZクランク』へと繋がっていく。
創業以来、30年以上にわたりルアーフィッシング業界の最先端を走り続けるメガバス。自社製造を行うルアーメーカーとしては国内外有数の歴史を誇り、その蓄積されたノウハウも世界随一。そんなメガバス&ア[…]
もちろんメガバスのクランクベイトはなにもZクランクの1種類だけではない。
なかでも『ディープX』は、そのエポックメイキングな設計と、高い完成度で今なお定番ルアーとして君臨し続けるロングセラー中のロングセラーシリーズだ。
しかしそのディープXは、メガバスの起源とも呼べるZクランクとはまた違った系譜のクランクベイトとなることをご存知だろうか?
伊東「クランクベイトの新しい方向性の追求とでもいいましょうか」
時は1990年まで遡る
当時はまだまだ外国産のルアーこそが至高とされた時代。
国産ルアーはその多くが、彼の地のものを、言わば『焼き直し』したものだったという。
伊東「当時のアメリカ製クランクベイトは、大半が強めのウォブルアクションでした。ウォブリングが悪いとかではないのですが、この動きの場合どうしても潜行時に水を逃してしまうため、深く潜らせることができなかったんです」
そこで伊東さんが注目したのが、ウェイトによる姿勢制御。しかし…
伊東「当時のクランクベイトにもウェイトに着目していたものは確かにあったと思います。でもそのどれもが、飛距離や潜行角度、アクションのいずれかに特化させる目的をもったウェイトでした」
伊東さんが着目したのが重心移動だったのだ。
伊東「初代のZクランクにはすでにアクション変化のための重心移動システムを搭載していましたが、その『重心移動』を使ってもっと効果的にクランクベイトを使えるようにならないかと考えたんです」
当時といえば、すでにタックルハウス社のK-TENに磁着式の重心移動システムが搭載されていた時代。
飛距離を向上させつつ、スイム時には磁石によってウェイトが固定されることでアクション時にウェイトが暴れる心配がない優れものだ。
伊東「ですが二宮さん(K-TEN開発者)とは違う方法を取りたかった。というか、目的が違いました。目指したのは、よく飛び、よく潜り、よく泳ぐクランクベイト。いわばディープクランクの形態シミュレーションだったわけです。そのためには、それまで特化させることで実現していた、飛ばすためのウェイト、潜るためのウェイト、泳がせるためのウェイトを同時に搭載する必要があったんです」
右を向きながら左を向くような、矛盾ともいえる発想を前にして、解決の糸口が見つけられないなかもテストは続く。
そしてある冬の日。
事件は釣り場で発生した。
伊東「浜松の冬の爆風を突き抜けられるキャスタビリティをもとめ、様々なサンプルをテストしていたんです。スプリングを使ってみたり、K-TENの逆バージョンを試したり、複数個のウェイトを入れてみたり…。ありとあらゆるものを試してみていました」
しかしこの時期の伊東さんは多忙を極めていた。
テストサンプルの作成を進める傍ら、製品製造や会社の経営に営業、取材…。
メガバスが会社として軌道に乗り始めていたため、伊東さんは1人で何役もの作業をこなしていたのだ。
伊東「疲労も限界をむかえたのか、うっかして堰堤から滑り落ちてしまったんです。気がつくと、激しい衝撃でコンクリートに叩きつけられて血だらけになっていました。そしてそのかたわらには、それまでテストしていたルアーが砕け落ちていたんです」
そして次の瞬間、落下した痛みなど吹き飛ぶような衝撃が走ることとなった。
伊東「砕けたテストサンプルの内部構造を見て、追い求めていた新たな『重心移動システム』がひらめいたんです。そこからは大急ぎで会社に戻りました。車のガラスに息を吹きかけて曇らせて、そのひらめきを忘れないように血だらけの指でメモしながら…」
そして生まれたのが、『多目的重心移動(PAT.)』だった。
多目的という言葉に込められたのは、まさしく「飛ばす」、「潜る」、「泳がせる」。伊東さんが追い求めていた、まさにそのものだ。
伊東「キャスティング時にはボディ後方へと移動して後方重心となり、飛ばすことができます。着水後、リーリングを始めて潜り始めた際には鼻先近くまで移動して前方重心となり、ウォブリングを抑えた前傾姿勢で素早く狙ったレンジへと潜らせることができる。そして潜りきってルアーの姿勢が水平に近づくとウエイトがセンター付近へと移動。ロールを主体としたより深いレンジの魚へとアピールできるアクションを発生するわけです」
この相反する3つのポジショニングを実現するために、前後に移動するウエイトをアクション時のみ固定する機構として『BLH(バウンサーロックホルダー)』も同時に開発している。
こうして、世紀の発明にして釣り業界における重心移動システムブームのきっかけとなった『多目的重心移動』を搭載し、1993年、『ディープX200』が誕生したのだった。
ディープXの系譜
1993年:ディープX200
それまで一般的だったウォブリング主体のクランクベイトからは大きく離れたメガバスオリジナルのクランクベイト。純国産クランクベイトのはしりともいえるだろう。
伊東「クランクベイトだけどクランクベイトじゃない。クランクシャイナーともいうべき形状で、オイカワやワタカといったベイトをイメージしています。アクションはわかりやすくいうとローリング&ハイピッチバイブでしょうか」
内蔵する『多目的重心移動』に関しては先述の通りだが、そのほかにも様々な肝が隠されている。
伊東「例えば空気抵抗を受けにくいリップの位置。キャスト時にボディのスリップストリームの中に入る位置に収まるようにデザインしていますから、大きなリップでもキャスタビリティに影響を与えにくい。また、アームズを皮切りに高弾性ロッドが増えていく時代を見越し、そういったロッドでも使いやすい設計にもしています。これらは現在多くのクランクベイトで用いられているセオリーです。ディープXでクランクベイトを学んだ人も多いのではないでしょうか?」
ディープX200といえば、何度かファインチューンを行ったことでも知られている。
左から最初期型、初期型、中期型、後期型
伊東「フックがラウンドのロングシャンク、ワイドゲイプ、カツアゲへと変わったり、アイがシールアイからリアルアイに変わったり、ウエイトがタングステンになったりと、時代の変化とともに少しずつ変えてきました。その中でも特に大きかったのはリップの形状とアイの位置の変更です。実は初期のものはロールウィグリングアクションだったのですが、ボトムに堆積する枯れ植物に潜り込んで泳がなくなることがあったんです。そこでリップとアイを変えることで、ロールウォブリングにファインチューンして改善したんです。1996年以降のモデルですね。もちろん、売れているものに弱点が発覚しても、それを言わずに売り続けることはできたと思います。でも無視できなかった。売り逃げはしたくなかったんです」
そのほかにも、タングステンウェイト化した翌年の2002年モデルからはより重心を一極化させるためにガラスラトルもオミットするなど、ロングセラーであり、だれもがその実力を認めるディープX200は時間をかけて、本当の『ディープX』になっていったのだ。
1994年:ディープX100
200の誕生から遅れること1年。
よりシャロ―に対応する『ディープX100』が誕生する。
伊東「これはディープX200を作る際に得た知見を活かしています。それからZクランクのタイプ2の継承ともいえるシャロ―クランクで、小規模フィールドにもマッチします。アクション的にはタイトオーバーロールアクション。200よりも小さくなった分ファットにして浮力を持たせるようにしているんです。ビジュアルはキャラ付けも含め、バスっぽくしています」
左から最初期型、初期型、中期型、後期型
200同様、100に関してもファインチューンが施されており、アイやフックの変更のほか、当初はロールウィグリングだったものが、2000年からリップ形状を変更し、ロールウォブリングへと変更されている。
なお、2001年にタングステンウエイトを搭載した200に対し、100はタングステン不採用が現行モデルとなる。これは100のボディ形状の場合、タングステン素材採用によるウエイト小径化のメリットが見込めないことに起因する。
1994年:ディープX201
伊東「200の亜種ということで、当初はスタッフだけが持っているアイテムでした。サスペンド~シンキングの設定になっていて、デッドスローの浮かせないクランキングが主な使いどころ。タフったバスにすこぶる強くて、動けないバスにぶつけるように巻くのが肝でした。ナチュラルプロブルーなど、淡いカラーが多くラインナップされていた点も通常の200と異なる点です。読みは”ニーマルイチ”」
同年に登場しているライブXリバイアサンに近いコンセプトだが、時代が早すぎたのかあまり受け入れられず、2年間限定販売の激レア品となった。
2009年(2010年):ディープX300(ディープX150)
100、200からはかなり時間がたって登場したのが300。
琵琶湖ガイドなら絶対に持っているといわれる名品中の名品だ。
伊東「当時メガバスチームだったアーロン・マーテンスやルーク・クローセンが欲しがったのが開発のきっかけでした。紀伊半島のダムに通って作ったのですが、この時は100や200のときのような手探り感はもうありませんでした。むしろ、アメリカの試合で使うことが前提だったため、失敗が許されないというか、遊びもなかったですらかね。それまでに培ってきたディープクラフトエンジニアリングの最適解を具現化しました。死角はありません」
事実、その性能は瞬く間に認められ、今やディープクランクを代表するルアーのひとつとなっている。
伊東「またほぼ同じタイミングで150も作っています。100や200と違ってもっとウォブリングに寄せた動きになっているのはボディがより球体に近いから。浮力と水圧が喧嘩することで強いアクションが出やすい設定になっているわけです。敢えて言うなら、ディープX300のコンパクト版でしょうか」
2012年:ディープシックス
伊東「ディープX300よりももっと深いレンジを狙いたい、という要望に応える形でつくったのが『ディープシックス』です。6mレンジが狙えるスペックですが、メインは水深5mのストラクチャーへ確実にコンタクトさせられることが狙いです。より水圧のかかる深場で使うためリップが薄くなっており、水キレをよくしたオーバーロール&ややウォブリングアクションです。また、水圧が高い場所でもヒラ打ちさせやすくするためにBLHは緩めに作っています」
2018年:LBOモデル
LBO2の登場に併せて、ディープXの100と200にはLBO搭載モデルが登場している。
つまり多目的重心移動がオミットされているのだ。
これにはどのような狙いがあるのだろうか?
伊東「多目的重心移動はルアーに内蔵するメインウエイトが移動するのですが、それはほかのメーカーでもなかなか見かけない機構です。この”メインウエイトが移動”、というのがLBOにつながっていきました。そしてハイドロダイナミクスの追求。この2点が合わさることで、重心を3段階に動かす必要がなくなったんです」
飛ぶためのウエイト、泳ぐためのウエイトはLBOが担い、ハイドロダイナミクスの追求により、潜らせるためのウエイトが不要になった成果。それがディープX100とディープX200のLBOモデルなのだという。
伊東「オリジナルモデルよりもより大きくロールするようになっていますが、アクションピッチは変わりません。それなのに巻き抵抗は小さくすることができています。なお、どんなルアーでもLBOを搭載すればいいかといえばそうでもなくて、例えばディープX300にはいれてもさほど意味がないでしょうね。よりフラットなボディで、フラッシングを活かしたいルアーこそ、LBOが活きるというのが現在の考えです」
ディープXを使いこなすために
ディープXシリーズを使う上でまず意識したいのはそれぞれの潜行深度だろう。
ベースとなる4モデルでいえば
100:3m以浅
200:4.5m以浅
300:5.2m以浅
Six:6m以浅
が活躍の場となるという。
伊東「水深10mの4mレンジを泳がせる、といった中層はもちろん得意ですが、深く潜るクランクベイトを浅い場所で使う、いわゆる”オーバークランク”的にも使えます。ディープXはスタックしづらいし、左右にダートするようなアクションも披露しますからね。おすすめのロッドはディープX100~200ならデストロイヤー F3.1/2-610X Zクランクエルザイル、200~300、Sixはデストロイヤー F5-70Xマッドブルです」
そして基本にして極意も。
伊東「巻くだけでも釣れるクランクベイトですが、基本は何かに当たったら止める、あるいは巻くスピードを緩めることがポイントです。こうすることでディープXはヒラ打ちしながらスタックを回避して、それが魚への誘いになります。それからワームのように使うのもお勧めですね。特にLBO搭載モデルは、コンタクトしたらロッドをゆっくりと立てて上げる。これだけでもディープXの強みを体感できると思いますよ」
『深い』仕事だったディープX
誤解を恐れずに言うのならば当時の日本にルアーメーカーは無かったと、伊東さんは振り返る。
販売されていたのはほとんどがアメリカから輸入してきたのものであり、日本で作られた製品だとしても、その多くがアメリカのルアーをまねたもの。
商社的に販売していることがほとんどで、ルアーをゼロから生み出せているわけではなかったのだから。
そんな中、伊東さんはそのままではいけないと考えたのだ。
伊東「日本でバス釣りが発展していくためには、欧米にはないものが必要でした。そうでないと、いつまでたってもアメリカには対抗出来ないし、メガバスも存続していけない」
それはいばらの道だったはずだ。
先行者はいない、ゼロからのスタート。しかも対抗すべき存在はあまりにも巨大だったのだから。
伊東「でも日本で『メーカー』を起こした責任とでもいいましょうか。必死に取り組みました。結果として、ルアーデザインにおけるセオリーの6割強は確立したのではないかと自負しています。それも1990年~2000年くらいまでで大体やりきれたでしょうね」
その熱意は現代に続く技術そして設計思想の礎となった。
そしてそれを証明するかのように、伊東さんは2001年にグッドデザイン賞を受賞している。それも中小企業庁長官賞という特別賞を。伊東さんの思いは一般社会にすらも認められたのだ。
生み出されたルアーの名は『ディープX』。
そこには、『ディープ』な仕事をしたという思いが込められている。
MEGABASS ENCYCLOPEDIA III
創業以来、30年以上にわたりルアーフィッシング業界の最先端を走り続けるメガバス。自社製造を行うルアーメーカーとしては国内外有数の歴史を誇り、その蓄積されたノウハウも世界随一。そんなメガバス&ア[…]
創業以来、30年以上にわたりルアーフィッシング業界の最先端を走り続けるメガバス。自社製造を行うルアーメーカーとしては国内外有数の歴史を誇り、その蓄積されたノウハウも世界随一。そんなメガバス&ア[…]
創業以来、30年以上にわたりルアーフィッシング業界の最先端を走り続けるメガバス。自社製造を行うルアーメーカーとしては国内外有数の歴史を誇り、その蓄積されたノウハウも世界随一。そんなメガバス&ア[…]
創業以来、30年以上にわたりルアーフィッシング業界の最先端を走り続けるメガバス。自社製造を行うルアーメーカーとしては国内外有数の歴史を誇り、その蓄積されたノウハウも世界随一。そんなメガバス&ア[…]
※本記事は”ルアマガプラス”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。
- 1
- 2