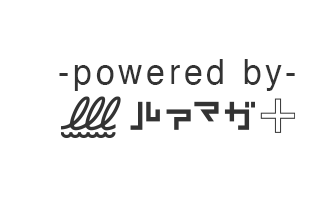今やバス釣り業界のトップメーカーのひとつである琵琶湖生まれの「DRT」。売れ線はやはりタイニークラッシュだが、実はDRTのロッドにもファンが多い。今回はそんなDRTのロッド「アーテックス」にまつわる対談の様子を紹介しよう。
●文:ルアマガプラス編集部
白川友也
しらかわ・ともや/ご存知、DRT代表。幼少期から人とは違ったセンスの持ち主で、青春時代はスケボー、音楽活動に打ち込んだ。20歳くらいから琵琶湖通いが始まり、30歳の頃に滋賀へ移住し、ディビジョン(DRTの前身)を立ち上げた。初期の業態はロッドカスタムからスタート。かつては岸釣りがほとんどだったが、今ではボートがメイン。
奥地渓希
おくち・けいき/岐阜県生まれ、滋賀県在住の28歳。以前は岐阜で古着屋などの仕事をしながら、琵琶湖の東岸に通っていた。バス釣りはビッグベイトからフィネスまでオールジャンルで挑む。また、丸型アンバサダーを好んで使用する。バスの最大魚は66センチ、5800グラムをフレンジーにて。
橋本蒼士
はしもと・あおし/滋賀県生まれ、在住の26歳。地元が奥琵琶湖近くなので、今も湖北エリアがホーム。岸からのビッグベイトが好きで、クラッシュ9、タイニークラッシュを一年中使う。リールはどちらかといえばシマノ派。バスの最大魚は61センチ、5300グラムをブルフラットにて。
琵琶湖における理想のロッドとは?
DRT代表の白川さんとスタッフのおふたりに琵琶湖のバスタックルをテーマに語っていただこうという当企画。
まずはロッドのお話から。
琵琶湖における理想のロッドとはどんなものだと考えますか?
奥地渓希(以下、ケイキ)「一番は安心感。使っていて安心できるというのがなにより大事。狙っている目標が世界記録なので、その魚と闘えるサオじゃないと絶対にダメ。絶対的な強さはありつつ繊細さもある。そういうロッドに今まで出会ったことがなくて。僕が初めて『これなら大丈夫』って思えたのがアーテックスだったんですよ」
橋本蒼士(以下、アオシ)「僕もやってるエリアがエリアなんで、遠投したり、深いところもやる。さらに魚をリフトできるパワーと感度が必要になる。世界記録級のヤツがいつくるかわからないし、掛けても獲れなかったら意味がないですからね」
白川「理想のロッド…僕は全体にバランスが良ければいい。具体的には持ったときの持ち重り感をなくすこと。実際には重量があってもバランスが取れたサオを作る意識をしています」
バランスのよさはアーテックスの特徴ですね。
白川「アーテックスはどれも世間でいうところのキツいテーパーなんです。そういうサオは手元に重心がくるし、バットが絶対に強くなる。グリップパイプも今主流のサオよりもウチのは太いですね。あと、ガイドも極力少なく、最低限にしています。その方が糸抜けがいいのと、ウチは感度も求めているので、ガイドは数が少なくバランスが取れている方が感度がいいと思っている」
やっぱり琵琶湖はロングロッドが有利?
アーテックスはほとんどが7フィート台後半とかなり長いのですが、琵琶湖の釣りではどのようなメリットがありますか?
白川「僕は今ボートメインでやってますけど、オカッパリとなにも変わらない。長いロッドのほうが自分の釣りに合ってる。ルアーを通すコースも修正しやすいので。それに慣れちゃうとやっぱり使いやすい」
ケイキ「長いロッドはできる釣りの幅が広いというか、投げられるルアーの幅が広い。機動力が落ち
るのでオカッパリに何本も持っていくのが好きじゃなくて、わりと一本でなんでもやりたいので」
アオシ「琵琶湖はブレイクが遠い場所も多いので、ロングロッドの遠投性は有利ですよね。あとは、クラッシュ9でカバーを撃ったりするのは長いほうがコース取りはしやすいですし」
白川「野池とか入り組んだ場所だとショートロッドが使いやすい場面はあると思うんですけど。ケイ
キは水路とか険しいところに入っていくけど、それでもショートロッドを作ってほしいとは言わないよね」
ケイキ「むしろロングロッドだから獲れる魚が増えた気がします。水辺とのディスタンスが取れたり、岸から離れた状態でも足元までしっかり引ける」
白川「うしろに振り幅がないのに足場が高かったりするもんな。ルアーをきっちり足元まで泳がせたいときはロングロッドが有効。あと、デカい魚が掛かったときは長ければ長いほどやり取りがしやすいよな」
DRTはスタッフ全員がロッドビルダーなのだ
DRTでは今も社内でロッドの組み立てを行っていますよね?
白川「社員全員がロッドを作れます。みんなロッドのことをよく知っていますし、パーツの重さも肌感でわかっている。うまく言葉にできないかもしれないけど、感覚的なものはみんなあると思います。最近は『みんなが欲しいサオを作ってみたら』って、そのへんに転がっている好きなブランクを使って、遊んでます。僕がいいなと思えば商品化されるかもしれませんね」
ケイキ「サオ作りはすべての工程が難しいですね。自分が作ってみたい試作ロッドを作らせてもらうんですが、いざ形にして使ってみると思い描いたものとまったく違ったりする。イメージを形にするのはすごく難しいです」
アオシ「僕もサオ作りをしていますが、考えるところから組み立てまで全部難しいですね。いざ完成しても重たくて感度がない…とかよくあります」
白川「理想を追求してもなかなかたどりつかないってあるよな。でもたまに『これめっちゃいいやん』っていうのもできる。僕はモノ作りを好きでやっているけど、ワンオフって実は簡単なんだよね。世にひとつしかないモノを作るって、自分が思った通りに作ればいいだけなので。一番難しいのは量産。人間が作っている以上必ずズレが出る。それを揃えて同じモノを作るというのはすごく難しいよ」
これまでは白川さんが欲しいロッドを作るというスタンスだったと思うのですが、今後、ユーザーの声に応える形でのモノ作りをすることもありますか?
白川「これからも自分たちがストレスなく使えるモノを世に送り出して『皆さんどうですか?』っていう感じです。ユーザーさんの好みに寄せるというのはないですね。結局自分もケイキもアオシも琵琶湖の大きい魚を求める釣りをしたいので。でも、同じような釣りをしていると、求めるモノは似てくると思いますよ」
なみに、琵琶湖以外で釣りをするときにアーテックスに対して思うところはありますか?
白川「僕は正直、もうちょっと弱いサオが欲しいなと思います。なので、遊べるサオも作っていますよ。それ以外は琵琶湖の釣りをそのままやりに行ってますね。アオシなんか渓流とか海もよく行くもんな?」
アオシ「でも結局琵琶湖がいいってなっちゃいますね」
ケイキ「そういや、地元に帰ったときに、五三川に行くんですよ。琵琶湖の釣りをそのまま持っていくと、そこのデカい魚が反応する気がしますね。普段見られないような魚が釣れたりします」
若いおふたりは他社のロッドにくらべて、アーテックスの特徴はどう感じていますか?
アオシ「僕はあんまり他社のサオを使ったことがないんです。ルアーは使いましたけど…」
ケイキ「感覚的にいうと、サオが体の一部のような…」
白川「たぶんですけど、ウチのサオってあんまり評価がないんです。ないのかできないのかわからないんですが、僕は持っていて違和感がない。『なにが違う?』って聞かれても答えられない。リールシートにしても癖がない、違和感がないからなにも思わないんです」
ケイキ「確かに、使っていても『ここがこうだったら…』っていうのが出てこないですね」
アーテックスを象徴する名作2機種
アーテックス R2 A710CXHF(DRT)
「クラッシュ9みたいな大きいビッグベイトからボトム系の釣りまで使える。感度がいいので底の起伏を感じやすいし、なによりパワーがあるので、獲れる、という安心感があります」(アオシ)。
「元々ジグ系ロッドでした。岸からラバージグや高比重ノーシンカーを遠投したり。その先で6/0~7/0フックを貫けるようなアクション。パワーがあるサオなので300グラムくらいのジャイアントベイトもキャストできる。そんなロッドに合わせて、クラッシュ9が生まれました。操作系ビッグベイトにもバッチリハマるようなアクションです」(白川)。
アーテックス ボーダーパトロールA800CMHRF(DRT)
「ボーダーパトロールは巻きモノ用ですね。6~7インチくらいのシャッドテール、スイムジグ、ちょっと大きめのクランクベイトとか。カバーを撃ったりK9クラスのビッグベイトならR2、ウェーディングもR2。スイムジグなどの巻きモノ系、タイニークラッシュにはボーダーパトロールを使っていました」(白川)。
※本記事は”ルアーマガジン”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。