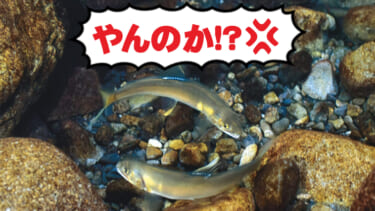●文:ルアマガプラス編集部
アユとは?
アユは、キュウリウオ目アユ科に分類される魚。その姿の美しさと、独特の香りから「香魚(こうぎょ)」とも呼ばれ、古くから日本の清流を代表する魚として親しまれてきた。また、寿命が基本的に1年であることから「年魚(ねんぎょ)」という別名も持つ。釣り人にとっては、夏の風物詩であり、その独特な釣り方と食味から絶大な人気を誇る。
アユの生態
アユは川で生まれ、一度海(または湖)へ下って成長し、再び生まれた川へ遡上して産卵するという“両側回遊”の生活史を持つ。川の上流域から中流域の、水質が良好で流れの速い瀬に生息する。成魚の主食は、石に付着する良質な珪藻類である。この餌場を確保するため、自分の縄張りに侵入してくる他のアユを激しく追い払うというとても強い縄張り意識を持つ。この習性を利用したのが、日本独自の釣法「友釣り」だ。
水質がよく、流れの速い川がアユの生息域となる。
アユの釣りシーズン
若アユシーズン(解禁~7月上旬)
多くの河川で釣りが解禁される6月頃から始まるシーズン。まだアユのサイズは小さいが、群れで行動していることが多く、比較的釣りやすい。瑞々しい香りと骨の柔らかさがこの時期のアユの魅力だ。
盛期(7月中旬~8月)
梅雨が明け、水温が上昇するとアユは急激に成長し、縄張り意識がもっとも強くなる。体高のある見事なアユが、瀬の中で活発に苔を食む姿が見られるようになる。「友釣り」の醍醐味をもっとも味わえる最盛期だ。
落ちアユシーズン(9月~禁漁期)
産卵を意識したアユが川を下り始めるシーズン。「錆アユ」とも呼ばれ、体には婚姻色が現れる。体力を蓄えているため、力強い引きが楽しめるが、縄張り意識は薄れるため釣り方には工夫が必要となる。
アユの釣り方
アユイング
近年登場した、アユをルアーで狙う新しいスタイル。おとりアユを使わず、アユの形を模した専用ルアーを操作して野アユを掛ける。友釣りに比べてタックルがシンプルで手軽に始められるため、若者を中心に人気が高まっている。
仕掛け例
竿:アユイング専用ロッド/エギング用ロッド
ライン:PEライン 0.4号~0.8号
リーダー:フロロカーボン 1.5号~2号
ルアー:アユイング専用ルアー(フローティング/シンキングなど)
その他:ルアーの後方にチラシ針やイカリ針を接続する
友釣り
アユの強い縄張り意識を利用した、日本伝統の釣法。生きた「おとりアユ」の鼻に鼻環を通し、腹部に逆さ針を打ち、野アユの縄張りへ泳がせる。縄張りを守ろうと攻撃してきた野アユを、仕掛けに付けた掛け針で掛けるという、とてもゲーム性の高い釣りだ。
おとりアユで野アユの縄張り意識を利用して釣る『友釣り』。
仕掛け例
- 竿:アユ友釣り専用竿(8m~9mが一般的)
- 水中糸:フロロカーボン/ナイロン/複合メタル/メタルなど
- 仕掛け:鼻環/中ハリス/サカサ針/ハリス/掛け針(イカリ針やチラシ針など)で構成された完全仕掛けが市販されている
おとりアユは釣具店で販売されている。
アユの食べ方
塩焼き
アユの食べ方として、もっとも代表的でその風味を存分に味わえる。独特の香りと、ほろ苦い内臓の味が絶品。ヒレに化粧塩を施し、踊り串を打ってじっくりと焼き上げるのが基本。蓼(たで)の葉をすり潰して酢と合わせた“たで酢”を添えるのが伝統的なスタイルだ。
アユといえば塩焼き。
天ぷら
とくに骨が柔らかい若アユは、天ぷらにすると頭から丸ごと食べることができ、とてもおいしい。サクッとした衣と、ふっくらとした身のコントラストが楽しめる。
鮎飯
焼いたアユを丸ごと1匹、またはほぐして米と一緒に炊き込んだご飯。アユの上品な出汁が米一粒一粒に染み渡り、贅沢な味わいとなる。
うるか
アユの内臓を塩漬けにして熟成させた塩辛。「苦うるか(内臓のみ)」と「子うるか(卵巣)」などがあり、濃厚な旨味と独特の苦みが特徴の珍味。日本酒の肴として珍重される。
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。
最新の関連記事(アユ)
ハイコスパ!アユイングを徹底的に楽しめるモデルが登場。 近年人気急上昇のアユイング、鮎釣りはハードルが高そうなイメージがあるが、ルアーで釣れるならやってみよう。というアングラーが増えてきている。 その[…]
アユイング最高峰!「アユイングEX」 DAIWAからアユイング最高峰のロッドとして2025年に登場する「アユイングEX」は、より多くのアユを“追わせて掛ける”というコンセプトのもと開発された。 ルアー[…]
力強いウォブンロールで野アユを威嚇するフローティングシャッド 九嶋さん「シリーズ名は「アユラシック」と言って…ま、ご想像の通り「アユらしく」ということでしょうか(笑)。まずは『シャッド110F』ですが[…]
水中写真で見るサカナの生態:アユ編 【Target Profile】 アユ 北海道から九州まで全国の河川などに分布しているアユ。清流の女王と呼ばれるほど清楚で気品のある川魚だ。1年で一生を終えるいわゆ[…]
【THEフィッシング】シーズン到来!気軽に手軽にアユイング アングラーは、アユイングの第一人者、木森直樹。エギングのエキスパートでもある木森は、ルアーの知識を活かして、全国の川で「アユイング」を研究中[…]
人気記事ランキング(全体)
21ナスキーから5年ぶりのモデルチェンジ 「ナスキー」はシマノの汎用リールではエントリーモデルという立ち位置だが、価格と性能面で非常に高いバランスがとれており、入門者だけでなく中上級者も使うほどの人気[…]
今回は利根川へ! 各種テストと、取材下見です。状況としては、どこに行ってもあまり良くない状況ですね・・・。次号ルアマガのバス釣り真相解明実釣編にも書いたのですが、秋は「良い水を探す」のがキーワードとな[…]
釣りの可能性を広げる、“つながる”リール DAIWAから登場する「ソルティガIC 300-C」。DAIWAのオフショアフラッグシップリールであるソルティガについにDAIWA CONNECTEDが採用さ[…]
乗らないバイトとはお別れ。 アグレッシブなバイトで水面が炸裂するも、乗らない! そんなトップゲームでの悩みを減らすために、開発されたのが、「クローフック」を搭載した「ビグロ SS95」だ。 クローフッ[…]
三国・鷹巣エリアでのティップエギング釣行と準備 ルアマガプラスの読者の皆さん、はじめまして! 清水彩香です! 初の釣行レポートのテーマは、私のホームフィールドでもある、三国・鷹巣エリアでのティップエギ[…]
最新の投稿記事(全体)
河口湖はかつてないほど減水中! 皆さんこんにちは!! 河口湖ガイドのトミーです。 今週の河口湖情報をお届け致します。 この一週間はかなり暖かい日が続き、11月末とは[…]
アングラーのための高機能インサレーションジャケット。冬の釣行を快適に制する 冬のオフショアジギングやロックショアゲームといった、寒冷下でもアクティブに動き続ける釣りには、高い保温性と自由な動きを両立す[…]
DAIWAの最強フラッグシップ機『ソルティガ』 DAIWAのソルティガは、マグロやGT、大型ヒラマサといった大物をターゲットとするための、DAIWAスピニングリールの頂点に立つフラッグシップモデルだ。[…]
スロージギングの完成形! メジャークラフトから感度と操作性を追究したスロージギングロッド「ジャイアントキリング7G」が誕生。妥協のない素材選定と設計により、スロージギングを極める1本に。 ブランクスは[…]
今回は利根川へ! 各種テストと、取材下見です。状況としては、どこに行ってもあまり良くない状況ですね・・・。次号ルアマガのバス釣り真相解明実釣編にも書いたのですが、秋は「良い水を探す」のがキーワードとな[…]
- 1
- 2