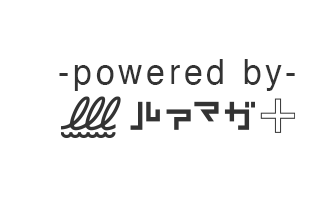長年、数多くのバスロッドを世に輩出してきた日本を代表するロッドビルダーであるレジットデザインの鬼形毅。そして、オカッパリメーカーとしてバスロッド「グラディエーター」の販売から産声を上げたレイドジャパンの金森隆志。意外にもほぼ初対面に近いというこの二人。バスロッドへの熱意とこだわり、そしてその未来について語り合う。
●文:ルアマガプラス編集部
profile
金森隆志(かなもり・たかし)
オカッパリのプロアングラーとして一世を風靡し、2011年にバスタックルメーカー・レイドジャパンを設立。最初のプロダクトとしてオカッパリバスロッド「グラディエーター」をリリースした。1981年岡山県生まれ。
鬼形 毅(おにかた・たけし)
15年余りに渡ってティムコでロッド開発を担当。その後、2015年に飯高博文氏とともにレジットデザインを設立。後発メーカーながらワイルドサイドシリーズはその性能の高さから瞬く間に全国のファンを獲得した。1971年生まれ。埼玉県出身。
「オカッパリらしさ」を竿で表現したい
金森「実は鬼形さんとはお顔合わせは初なんです。よろしくお願いします。あ、まず先に言わせてください。鬼形さんは正真正銘のロッドビルダーですが、僕はロッドビルディングは全くできません!アングラーとしてこんなのがほしいっていうレイドジャパンの竿のプロデュースやディレクションをしているだけなので。もちろんうちの会社には僕の代わりにロッドビルドをしてくれる人間がいるので。その点ご了承ください!」
鬼形「ははは(笑)。こちらこそよろしくお願いします。でも会社としてはレイドさんの方が先輩なんですよね」
金森「レイドジャパンができたのが2011年。レジットデザインさんは何年目ですか?」
鬼形「うちは2014年創業、15年に販売開始で今年10周年。以前のメーカーでロッド開発担当をやっていたんだけど、脱サラして、飯高(博文)と自分たちのメーカーでロッドブランドを作りたいなっていうところから始まったのがレジットデザイン。レイドジャパンが出てきたときにすごくよく覚えていることがあって。すでに金森さんはオカッパリのスターだったわけですよ。僕は基本ボートアングラーで、オカッパリからは遠いところにいたから、金森さんは雑誌などのメディアで見る人っていう存在だった。その人が自身のブランドを立ち上げて、しかもその一発目の製品がロッドだった。それがすごくびっくりして」
金森「みんなに言われましたね。お前バカじゃないのって(笑)」
鬼形「元々、超人気のブランド(メガバス)を背負ってた人がロッドをイチからやるって、勇気がいることじゃないですか。うちも竿屋だからわかるけどさ、ビジネス的なことを言うと、軌道に乗っちゃえば竿って単価が高いからボンと上がるけど、コケたときが怖いよね」
金森「いきなりロイヤルストレートフラッシュを狙いにいったみたいな(笑)。もう博打ですよね。でも、ロッドからスタートさせるっていうのは最初から決めていたんですよ。僕にとってオカッパリスタイルを表現してみたかったのがまずロッドだったんです。例えばリアグリップひとつとっても、ボート用を意識した設計ってのが基本じゃないですか。これはほかの動画でも言ってるんですが、当時の僕はオカッパリをやってることに対するコンプレックスがすごかった。ボートアングラーやトーナメンターから蔑まれてるし、評価されない位置づけだなっていうのがあって。そして優れたアングラーや開発者はみんなボートでバス釣りをしていて、竿もそこから生み出されていた。当時そういうことがあって、当然レイドがルアーから入る選択肢もあったとは思うんですけど、オカッパリらしさを一番表現できるのは竿だと思っていたんです」
鬼形「いやね、日本のオカッパリに関して言うと、今のオカッパリのツートップと言っても差し支えない金森さんと川村(光大郎)さんが出てきた以前と以後で、日本のバスフィッシング史は全然違うと思うのよ。その前のオカッパリってなると村上晴彦さんのイメージが強くて、沖に向かって遠くに投げるとか、漁港でいっぱい釣るとかっていうのはすごいインパクトがあったと思うんだけど。オカッパリスタイルって何なの? っていう問いに、誰も答えをもっていなかった時代が結構長かったんですよ。ロッドについてもオカッパリ用って言われると、やっぱり村上さんのスタイルの影響で、川とか沼の対岸まで投げたいんですっていう長い竿がオカッパリ用って言われていて。そんな中、レイドがオカッパリ用を謳って出してきた竿はというと…」
金森「パッと見て(ボート用と)違いがわかる? って言われたらわかんないですよね(笑)」
鬼形「僕にとってはそこが面白かったの。それまでのみんながイメージするような7ft半とか長さがあって、リアグリップが長くて、ボーンって投げるような竿ではなかった。僕ね、そこがエポックメイキングだったと思っているんですよ。カナモと光大郎さんの登場で完全に時代のステージがひとつ変わった。オカッパリって日本の文化でしょ。ボートの釣りってアメリカから入ってきて、アメリカの釣りに合わせてみんないろいろ日本風にアレンジしてたけど、オカッパリは完全ジャパンスタイルじゃないですか」
金森「なんかもう鬼形さんにそう言っていただけると、すごく沁みます…」
オカッパリ用としてとがらせていった結果、極めてスタンダードで使い勝手の良い竿に仕上がっているのが面白い。
グラディエーターマキシマムの竿を興味深く観察する鬼形さん。
鬼形「オカッパリ用であろうとボート用であろうと、バス釣りの竿としてのコアな部分は変わらない」
オカッパリ用の竿とボート用の竿は存在するか
鬼形「そこは本当、すごいなと思ってて。だから今日、編集部の人からいただいたテーマにもあるんだけど、オカッパリ用の竿、ボート用の竿って何ですかみたいな話って、俺ら仕事をしてるとメディアからも一般の釣り人からもすごく聞かれるじゃない」
金森「これってオカッパリ用ですかとか」
鬼形「どっちかっていうとボート用ですかとか(笑)。僕、いつもそこの答えがわからなくて。そもそもオカッパリ用って何なの? ボート用って何なの? っていう。確かに、僕はボートで使いやすいように考えて作ることはよくあるけど、でも例えばレイドの竿がボートで使えないかと言ったら、そんなこと全然なくて」
金森「全然ない(笑)」
鬼形「実際にレイドの竿を使ってトップクラスのトーナメンターがいっぱい活躍しているわけですよね。逆にワイルドサイドだってオカッパリも全然できる。けど、カナモが作った竿は、やっぱりオカッパリの人には安心感があると思うんだよね。そこがすごい大事な点だと思うんですよ。だってカナモはオカッパリを知ってるし、さっき言ったようにカナモによって日本のオカッパリってワンステージ変わったはずだから。その人が作った竿は、それはオカッパリをやってる側からすると、とりあえずここから選べばいいんでしょっていうくらいの安心感があると思うなあ。レイドがスタートしたときにロッドから始めたってことに対して、俺は驚きと同時にめちゃくちゃイケてるなと思った」
金森「いやもう、鬼形さんのひと言ひと言が身に余りますよ。今すぐ家に帰って大声で叫びたいくらい嬉しいんですけど(笑)。ただ今もその当時も変わらないのは、オカッパリの優位性を生かせるように、その釣りがやりやすいロッドが欲しい。じゃあそれは具体的に何なんだ? っていう、ここが一番大事なんですけどね。オカッパリでやる以上、鬼形さんが先ほど言われたように、ビューンって遠くまで投げる必要がある。オカッパリは近づけないところが多いんで、やっぱり飛距離は必要。もうひとつは、足元で食わせることに対する性能。足元の護岸、ブレイク、カバーで魚がルアーを追い詰めやすい状況で食わせるというアプローチ。飛距離と足元での精度を上げたいってなるとこのふたつは本来、相反するんですよ。でもオカッパリでは1本で両方やりたい。その答えでもあるんですけど結構うちのグラディエーターって早い段階からソリッドティップを入れていったんです。そういったオカッパリの基本的なところを追求していくっていう部分が、竿作りの根っこにある。今もそこは変わりませんね」
鬼形「オカッパリ目線の竿っていうのは当然あるんじゃないかな。だけど、俺が思ったのはそういう考えで生まれたカナモの竿が、結果的にオカッパリで使おうがボートで使おうが全然問題のないプロダクトになっているのが面白いなと思ってて。極端にオカッパリ用っていう感じが全然しないんだよね。今ちょうどテーブルの上に置いてあって、ちょっと見せてもらっても、極めてスタンダードであり、オカッパリだろうがボートだろうが使い勝手の良い竿になっている。もっとオカッパリに寄せて、もう逆にボートじゃ使えないよねっていう竿が来るかと思ったら、グラディエーターは初期モデルからそうではなかった」
金森「たしかにそうですね」
鬼形「レイドの竿はそんなに何かに特化しているわけじゃないって正直見てて思うし、僕からするとそれがまたいいんですよ。僕が長く竿作りに携わってきて、さっきも言ったようによく聞かれるのはオカッパリ用ですかボート用ですかっていうことなんだけど…。同じバス釣りをいろいろと突き詰めて考えていくと、割と似たような結論に行き着くのかなと思っていて。確かにオカッパリは遠くに飛ばしたいシチュエーションがボートよりは多いとかの違いはある。だけど、バス釣りの竿としてコアな部分って実はほぼ同じなんじゃないかってね。今回、ふたりでバスロッドの対談をするってなったときに、その部分の理解が噛み合っていたほうがいいんじゃないかって思ったんだよね。同じバスフィッシングなんだから基本一緒でしょっていう」
金森「“オカッパリの優位性を生かせる竿”を目指すグラディエーターのコンセプトは今も変わっていない」
ワイルドサイドとグラディエーターマキシマムの同じレングスのスピニングを見比べる鬼形さん。鬼形「バスロッドは短いのにガイドがたくさんついているから竿に与える影響が大きい。それがまた個性の発揮のしどころだったりするんだけどね」
竿の「味付け」の違いを楽しむ
金森「確かに。例えば、同じカレーを食うにしても、インド料理系のカレー屋さんに行きますか、ココイチに行きますかっていう。いやいや同じカレーじゃんって。腹減っててカレー食いたいと思ったら、どっちを選んだとしてもカレーを食べたことには変わりない。でも、ちょっとやっぱインド風はこうだよ、でもココイチはこうだよっていう…。そこの本当にちょっとした『ニュアンスや味付け』に近いんじゃないかなって思うんです」
鬼形「そう。味付けの違いだと思う。竿を作っていてよく思うのはそのちょっとした味付け、例えばレングスが1in変わるとか、リアグリップの長さが5mm変わるとかで、劇的に使いやすさが変わってくるんだよね。そういった味付けの部分が、オカッパリに寄っているのか、そうではなくボートに寄っているのかっていう違いなんだと思う。使える使えないっていう次元の話では全くないのかなと」
金森「そう、使いものになるならないっていう次元の話ではない。竿ってもっと高度なものだと思うので。結局、鬼形さんが今言われたように、リアグリップの長さがほんの少し変わるだけでもニュアンスって大きく変わるじゃないですか。その細かいニュアンスまでご理解いただいて選んでもらえれば僕ら作り手側の人間としては非常に嬉しい。ただ、ここまでの話って、今これを読んでくれてる人が、どう受け取るかがすごく大事で。じゃあ別に何でもいいんだって思うのか、それともそこをこだわりたいって思うのか。そこの捉え方次第で、竿選びや釣りという遊びの面白さを凝縮できるかどうかに関わってくる部分なので」
ワイルドサイドの名竿のひとつ、ピュアグラスロッドのWSC-G66ML。クランキングに酔いたいならぜひ使いたい一竿だ。
フリッピングロッドの普遍性
鬼形「最近だとサイコロラバーのリアクションダウンショットで使うような『特化型』の竿もあるけど、バス釣りってそういうものが時々出てきて、そのまま定番になるものもあれば、ある程度の流行のあとに消えていくものもあるよね。例えばね、うちの竿の話をしちゃうと、フリッピングロッドを出したんだけどさ。これなんて、オカッパリの人にはほぼ縁のない釣りですよ。でも、俺はバスフィッシングの竿屋としてやっていく上で、フリッピングロッドは絶対ラインナップで持ちたいっていう気持ちが常にあった」
金森「フリッピングロッド、やっぱかっこいいですね」
鬼形「今日はそのフリッピングロッドの原型を持ってきたんです」
金森「いつの時代の?」
鬼形「1980年ごろ」
金森「僕が生まれた年だ(笑)」
鬼形「グラスでできてて。俺のフリッピングロッドコレクションの中の1本。当時フェンウィックの契約プロだったアメリカのD・トーマスさんって人がいて、彼は10ftとかのもっと長い竿でやってたわけ。要はもう垂らし釣りですよ。西海岸のカリフォルニアデルタというアシとかマットカバーがあるところで、もう連戦連勝してた。それを見たほかの選手が長い竿でチョンチョンやるのは卑怯だ、ダメだ規制しろってなった。そこでD・トーマスは一生懸命考えて、このフリッピングっていう動作を生み出し、その釣りができる最低限の長さっていうところで8ftまでは欲しいって言ったから、バスマスターでロッドは8ft以下っていうルールができた。そのときの作ったのがこの7ft6inのフリッピンスティックっていうロッド。これの何がすごいかっていうと、あの当時1970年代後半から80年代ってカーボンロッドが出始めで、まだグラスロッドも多かった時代なので、アメリカ人ですらガングリップの6から6ft半くらいのグラスロッドでワームを投げてボヨンボヨンってやりながら釣っていた中で、フリッピングしかできない竿を出しちゃってるところがまず発想としてすごい。当時からすればガチ釣りロッドなわけで(笑)。もっとすごいのが、リアグリップの長さとか、リールシートから元ガイドまでの距離とか、すべてにおいてフリッピングロッドとしてこの当時の段階で完成されちゃってるわけ。原型にして完成形。今フリッピングロッドを作ろうと思っても、このままのフォーマットでいいんです」
金森「ほお〜!」
鬼形「そこがやっぱりすごくて。ときにこういうことが起きるんですよ。流行の釣りだと思って作った竿が普遍性をもつっていう。この竿が80年ごろだからさ、それから40年以上の間にさ、フリッピングロッドが何パターンも出てくるわけ。フェンウィックでもいっぱい出てきてるし、当然俺も携わったフリッピングロッドって5〜6機種はある。でももうね、いろいろ変えたりして試すんだけど結局このフォーマットに落ち着くのよ。今回ワイルドサイドで作ったフリッピングロッドも、当然時代とともにガイドの径と数は変わるけど、全体としてはほぼ一緒。フリッピングロッドは、ある時代のある釣りに特化したものがフォーマットを作り上げて、何十年経っても、そのフォーマットが最適解になっている良い例だよね」
鬼形さんが持参したフェンウィックの「Flippin’ Stik Model 775-2」。1980年ごろに生産されたものだが、その完成度の高さから、現在のフリッピングロッドはこれをフォーマットに作られているものが多い。
最先端素材が良いという罠
鬼形「今の話に関連した例で言うと、素材とかガイドってまさに日進月歩で進化していて、特にカーボン素材って本当に良くなってるわけ。最近ならM40Xとかね。よく俺が言っているのは、釣り人からするとカーボンって釣竿に使われるものだと思っているかもしれないけど、そもそもは竿用じゃないんだよね。飛行機とか車とか、そっちの需要のほうが圧倒的に多いわけ。そうするとさ、そっちの業界では軽くて硬いが大正義なわけ。そうすると、軽く、硬く、強くなって何がいけないんだっていう理屈で素材メーカーさんは素材を進化させちゃうじゃない。だけど、僕たち竿屋は、バスロッドにとってそれが本当に良いかどうかはまた別問題だということを頭の片隅に入れておいたほうがいいと思うんだよね。例えばさ、ここにクランクベイト用のグラスロッドがあるわけですよ。これは100%ピュアグラスの竿」
金森「これ売れましたよね?」
鬼形「めちゃくちゃ売れた。グラスだけでうちに何本かあるんだけど、そのうちの一番真ん中の6ft6inのミディアムライト。グラスなんてさっきのフリッピングロッドと一緒で80年代からあんまり変わってないわけよ。グラスによって何種類かパターンはあるけれどね。今の時代はローモデュラス(低弾性カーボン)やグラスコンポジットとかあって、好みはあるにしても、それら最近の素材と比べて、この竿がグラス100%だから性能が劣っているのかと言うと、全然そんなことはないんだよね。なんならこっちの方がいいときがあるわけ」
金森「わかります。最先端が常に最良手とは限らないですよね」
鬼形「そうそう。それって、ロッドを作る側の人間としては、めちゃくちゃ肝に銘じておかなきゃいけないことで。最先端素材って聞くと使いたくなるのよ。ガイドも新しいのが出たら使いたくなっちゃうの」
金森「とりあえず組みたくなりますよね。どんなものだろうって」
鬼形「竿も軽くて強いはある意味正義なんだよ、絶対にね。当然重たい竿よりは軽い方がいいし、弱い竿よりは強い竿のほうがいい。でもそれ以上に大切なことは、その竿を使うことによって魚が釣れるようになっているのかという究極の問いにちゃんと答えられているかどうか。最先端素材を使うことで逆に使いにくい竿になってしまっている可能性もあるわけよ。だから、行き過ぎた進化はユーザー目線として必ずしもユーザーフレンドリーであるとは限らないと思っています」
ブランドコンセプトが竿作りのゴールを決める
鬼形「釣り竿って、ゴルフとか野球と違ってレプリカじゃないんですよ。プロが使っているものと全く同じものを一般の釣り人も買ったり使ったりすることができる結構珍しい道具じゃないですか」
金森「確かにそうですね」
鬼形「例えばゴルフって、本当に男子プロゴルファーが使っているドライバーなんて素人じゃ振れないんですよ。反発係数が高すぎてまともに振れない。でも釣りに関しては、カナモが使っているのと全く同じ竿をお店で買えるんだよね。それってすごくいいことなんだけど、作り手側としてはそれをちゃんとユーザー目線で作っておかないと、プロ専用になっちゃって一般の人には使いにくい竿になってしまう可能性がある」
金森「わかります。例えばミドストロッドを作ろうってなったときに、うちのスタッフの中でさえ経験値の差もあれば、動かし方の差もあったりして誰もがミドストできる竿を作ろうとなると…」
鬼形「違うよね。全く違うんですよ。だから、竿作りにおいてどこにゴールを設定するかっていうのは、作り手としてはとても大事なこと。これってブランドのコンセプトに関わってくる話なんですよね。トップアングラーが使うレーシングな竿を作って一般の釣り人にも使ってもらうっていうコンセプトがある一方で、俺なんかは一般の人が使いやすい竿を提供したいっていう気持ちのほうが強いかな。それを宣伝するために結果的にプロに使ってほしいってのもあるけどね。そうするとね、もう全然ゴールが違ってくるんですよ。もう本当にカリカリに尖ったレーシングなものだけを作りたいっていう作り手もいる一方で、俺はどっちかっていうと使い手をサポートする道具でありたいっていうコンセプトでやってるんで、投げにくい竿とかはあんまり作りたくないしね。さっきのグラスロッドで言うと、バイトの乗りの良さって人間側の技術でカバーできない部分だからグラスを使うわけ。掛かったらバレないとかも含めて、竿が助けてくれるっていう。僕はそういう部分をすごく大事にしている。あとは、アングラーの上達の手助けになるような竿作りっていうのは結構意識してるところかな。さっき出たフリッピングだったり、あとはリアクションダウンショットとかミドストとか。この釣りをやりたいってなったときに、レジットのラインナップの中にはそれに対応する特化型の竿が大体ある。あとはその釣りだったりテクニックがやりやすいように作っているつもり」
ここのギャップも最高ですね。
金森隆志
ここの良さをわかってくれる人はなかなかいないんだよ。
鬼形 毅
釣り具の中でも最も釣り人の個性が反映されやすいのがロッド。
コンセプトの魅力がファンを獲得する時代
鬼形「やっぱりね、オカッパリとかボートとかっていう分け方も一つのコンセプトだと思うけど、そのコンセプト作りが今の時代の竿作りで1番大事なところじゃないかな。なぜなら今の時代、正直に言うとメーカーごとに竿の違いを出すことって難しいんですよ。そりゃあ見た目は違うよ。だけどさっきも言ったように、使ってる素材はさ、カーボンならT1100Gです、M40Xですって、同じなんだよ。ガイドもそう。富士工業さんから買えば、ガイドもシートも同じものを買えちゃうわけ」
金森「あとは本当にもう各メーカーや作り手のニュアンスだったり味付け、それがいわゆるコンセプトだと」
鬼形「そう。同じマグロでもどう切るかとか、どう煮るか焼くかで変わってくるのと一緒で、コンセプトなんですよね。そのコンセプト設計がカナモの場合は、オカッパリっていうベースがひとつ入っている。レジットの場合は、ボート、そしてユーザーフレンドリーでワンランク上の使いやすさというのがある。コンセプトがはっきりしているメーカーさんの竿ほどファンはつきやすいと思う」
金森「今、鬼形さんが言われていることはすごくわかる気がして。俺、竿ってなんか政治や宗教みたいだなって思うことがあるんですよ。例えば、自民党、国民民主党とかあるように、世の中にいろんな宗教があるように、それに近い感じがする。自分はこのメーカーもしくはこの人の竿しか使いませんとか、このブランドに俺は共感するんだとか。あとは亀山ダムにロードランナーユーザーが多いように、ブランドコンセプトとフィールドが結びつくこともある」
鬼形「竿はそうだよね。『竿が人につく』のはすごくわかる。だって釣り道具の中で、竿とリールは看板みたいなもの。ぱっと見一番目立つしね。で、良くも悪くもリールはメーカーが少ないから選択肢がそんなにない。一方で竿はめちゃくちゃ選択肢が多い。自分の個性とか思い入れ、好きなアングラーとかブランドとかっていう共感の出しどころとしては、やっぱり竿が一番なんじゃないかな。竿の面白いところは、例えばレイドの竿で揃えてたら、誰がどう見たってカナモのファンなのかなとまわりの人は思うじゃない。実際は違うかもしれないけどね。竿にはそういう側面が絶対にある。釣り人個人のアイデンティティ(個性)と密接に結びついているんだよね。俺の好みはこれだよっていう個性を発揮しやすいのが竿なのかな」
酔える竿を見つけよう
鬼形「だから僕はそういう部分はすごく意識してて、さっきのグラスロッドの話にしても、もちろんグラスっていう素材がいいからグラスにしたんだけど、うちのこのグラスを買って、コンクエストか何かをつけてアメモノのクランクを巻いてるような人って自分がめちゃくちゃイケてると思ってるはず(笑)」
金森「いやでもね、それって本当に大事!」
鬼形「すっごい大事なんですよ。このセッティングでこのルアーを巻いてる俺って最高! っていう」
金森「酔えるってすばらしいことじゃないですか。それは道具が酔わせてくれるわけですからね」
鬼形「うちがピュアグラスロッドを出したときにはそういうコンセプトはあった。これがピュアグラスではなくグラスコンポジットだったら、あんなに多くのアングラーがレジットの方を向いてくれなかったと思う。例えばノリーズさんのハードベイトスペシャルにコンクエストをつけてる人はそれに酔ってるんだもん。そのタックルでクリスタルSを巻いてたらもう、超イケてるって思ってるわけじゃない? で、実際イケてるんだよ。あとはもう『来たぜ』って言いたいわけじゃない。そういう人々に、いきなりレジットのカーボンの巻きモノ竿使ってもらうのは難しい。でもピュアグラスは持ってないでしょって。これでイケてるクランクを巻いてグググってバイトが来て、なんか外掛りでハリ1本で獲れたらめちゃくちゃ痺れるでしょ」
金森「それはやばいっすね(笑)。しかも、口の硬いところにギリギリ針先がのっかってるだけみたいな」
鬼形「なんならバーブがちょっと見えてるくらいの浅掛りで(笑)。そうなると、もう釣ってる本人が、俺の竿選びは完璧だったって酔えるわけ」
金森「酔える竿って大事ですね」
鬼形「めちゃくちゃ大事」
金森「いやぁ、たまらない。ちょっと俺、興奮しすぎて今日寝れないかもしれない(笑)。自分もそうなんですよ、プロトロッドをテストしていて、俺の場合は魚のバイトを合わせたときに酔えることが多いかな。『あっ、これこれ』っていう」
鬼形「だってこのフリッピングロッドで1匹釣ってさ、しょうもないウンチクを語れるわけじゃない。ウンチクを語れるのも釣り竿の良さだよね。酔える竿を作ることが、自身のブランドを引っ張っていくことにもなるし、そのブランドの味になったりもすると思うんだよね。だってやっぱりね、さっきから話に出ているクリスタルSって、なぜか竿はハードベイトスペシャルを使ったほうがいいような気がするじゃない」
金森「何かそれ以外の竿でやるとすいませんみたいな(笑)」
鬼形「なんか間違ってるみたいなね(笑)。でも実際それはあると思うんだよ。もちろん竿としての性能が伴ってこそなんだけどそれこそがブランド力なんだよね」
10年後のバスロッドを想像する
金森「十年ひと昔と言いますが、今から10年先ぐらいまで見据えて何をやっていきたいかっていう竿の可能性の話。それって今後どんな釣り方が生まれてくるかが一番重要になってきますよね」
鬼形「竿作りに関していつも考えてることがあって、結局竿だけ先走ってもしょうがないんですよ。なぜなら、竿って釣り方に付随してくるものだから。テクニック、ルアー、あるいはフィールドの変化に対応させるわけだけど、ちょっと人より先取りするみたいな。竿作りに関しては一歩先ではなく半歩先ぐらいでいいのかなと思っています。ルアーは一歩先を行ってほしいんですよ。ルアー作りをやってる人って、もうとにかく誰よりも釣れるものを誰よりも先に見つけたいわけでしょ。竿はそのあとについてくるものなので。どっちかっていうと、10年先にどんな釣り方があるかとか、フィールドがどんな状態になっているかで未来の竿作りは変わってくると思う。単純にカーボンやガイドの素材が良くなるっていう話は容易に想像できるじゃない。絶対にそこの進化は止まらないから。でも10年後に求める一番大事なことはそこじゃなくて、やっぱりその竿を使って『俺かっこいい、俺の釣り超イケてる』って思えるかどうかだと思う。ただ、具体的にいろいろ釣り方に合わせて進化していかなきゃいけないっていう部分では、今後はPEラインがバスフィッシングにおいても相当普及すると思うんだよね。10年と言わず、この1年2年で急速に。もうすでに人によってはスピニングも全部PEの人っているでしょ」
金森「僕、9割PEです」
鬼形「でしょ。僕なんかどっちかって言うとフロロカーボンの食わせ能力を重視してる側ではあるけれど、でもやっぱりさ、耐久性とか細くて強いっていう点で言うと、PEのアドバンテージってすごいわけで。PEラインに対応させた竿はこれから3年ぐらいで各メーカーが真剣に考えなきゃいけないと思います」
金森「現に今年、うちからPEの竿が1本出るんですよ。江口俊介がここ数年、俺と一緒に竿を振る中で、PEでミドストができるロッドを作らなきゃ駄目だよねっていう話になって、この2年くらい江口が開発してきたものが、今年PEを軸としたミドストロッドとして発売します。PEでやるミドストってこうじゃないですか?っていう『提案』なんですよ。これがもうさらに2年3年経っていくと「こうじゃないですか?」が「こうです」っていういわゆる正解にまで辿り着くと思うんですけど。うちも今そこは正直チャレンジなんですよ、これが現状のレイド的回答ですっていう」
鬼形「それがまさに『半歩先』なんだよ。うちもね、ちょうど10周年だからチャレンジングなアイテムとして出すんだけど。スパイラルガイドなんですよ。いわゆるPEベイトフィネス用です」
金森「おお〜」
鬼形「6ft6inのミディアムアクションなんだけど、コシがないPEで軽いものをベースに投げようと思うと、どうしてもブランクスにラインが絡んだり張り付いたりする。だからできればガイドを下に持ってきたい。するとスパイラルセッティングがひとつの答えになる」
金森「ここイケてますね。この短い幅で元ガイドから3つ目までで一気に下まで180度スパイラルさせてますもんね。でも確かにこれぐらいギュッと持っていかないとどうしてもブランクスにラインが当たっちゃいますもんね」
鬼形「そう。できるだけ早い段階でガイドを下にしてあげる。要はブランクスの下にラインが通る状態をできるだけ長く作った方が綺麗に曲がってくれるんで。スピニングでやるパワーフィネスの弱点である投げにくさや手返しの悪さをPEベイトフィネスでカバーしましょうっていうところで、このセッティングをバチッと合わせてくるっていうのが、俺なりの半歩先なんだけどね。こういうPEベイトフィネスの竿とか、さっきのレイドさんから出るPE用のミドストロッドなんかは、今年注目すべき流れのひとつかな。おそらく似たようなコンセプトの竿を作ってくるメーカーはほかにも出てくると思う」
人気度ではなく釣り人やフィールドとのマッチングで竿が選ばれる時代が来る。
成熟し切った日本のバスフィッシングで求められる竿とは
金森「各カテゴリーの釣り方も釣り人自身も成熟してきたんだと思うんですよ。今日の対談で思いましたけど『名前がつく』ってすごいことだなと。例えば、パワーフィネス、ベイトフィネス、ホバスト、ジグスト…。最近だとパワーミドストって言葉も最高じゃないですか。そういったアプローチに名前がつけられることで、竿作りも同時に可能性が広がる。そういう新しいテクニックをお客さんも貪欲に追求しているから作り手の僕らも一緒に追求できる」
鬼形「新しいルアーや釣り方に合わせて竿も新しく生まれたり進化したりしていくっていう流れは今後も変わらないと思う。カナモが言ったように日本のバスアングラーは今、成熟期を迎えていると思う。バス釣りのキャリアを長年積んできている人たちが多いわけじゃない。そういう人たちが竿を買うわけだから、やっぱり細かいところにこだわり始めているのは間違いない。今はバス人口の多くが脱初心者化していて、こだわりがガイドセッティングとかそう言う部分にまで及んでいるのかなっていう気はする」
金森「そういう意味だとオカッパリのアプローチや竿の概念も成熟してきていると思います。より自分が行く地域やフィールドに合った、そこで精度が出せる、そこでのパフォーマンスが最大に発揮される道具は何だっていう。だからもうね、タックル・オブ・ザ・イヤーのときに、上位の竿って結局メーカーとか個人の人気の裏返しだよ、なんて言われ方をする一方で、僕はそれももう長くは続かないと思っていて。その地域、そのアングラー、そのアプローチによってどこのメーカーのどの道具が一番パフォーマンスが上がるんだ、自分に合っているんだっていう。もうこれだけ日本のバスフィッシングが成熟してくると、多分そういった価値基準に流れていくのかなって思います。いわゆるあの人が作った竿が人気だねとか、このメーカー人気あるよねとかっていう方向性はちょっと緩やかになってくるのかなと」
鬼形「竿に人気投票的な側面は絶対あるし、人気のアングラーが使っていればその製品が売れるとか人気のアングラーが使ってるからそれを使いたいと思う人がいるのは当然なんだけど、これだけバスアングラーが成熟してくると、自分が行くフィールドに合わない道具、あるいは釣果に直結しない道具は支持されないよね。そこはもう、バスバブルって言われていた時代とは絶対的に違う気がする。合わない道具は買わないし、実際にそれだと釣れないしね。最後に、今日の話で誤解しないでほしいのは、別にクランクベイトやスピナーベイトの巻きモノだけが酔えるって話じゃない。ライブスコープを使ってマイクロホバストで『おら、食わせたぜ』って酔ってもいいんです。その釣りで最高に酔える竿があればすばらしいことなので。そういう『俺、今超イケてる釣りをやってる』って思える竿に出会ってほしい」
金森「そのためには、鬼形さんも僕も釣り人として酔い続けなきゃいけないですね。メーカーとしてもこれで酔えますよって自信をもって世の中に言える竿を生み出していくっていう、そこに尽きると思うんで。今日は初めてお話しさせていただきましたけど、次は本当に酔えるものを飲みながら、ぜひ居酒屋で(笑)」
鬼形「そうしましょう(笑)」
鬼形毅&金森隆志SELECT
酔えるロッドミニカタログ
上:グラディエーターマキシマム GXT-70HC-ST ザ・マックス改
下:グラディエーターマキシマム GX-61ULS-ST マックスフィクサー
(ともにレイドジャパン)
プロトロッドのように極力ブランクスの装飾を排したデザインでコンマ何gの贅肉さえも削ぎ落としている。金森さんが絶対の信頼を置く右腕と左腕とも言える存在。
ワイルドサイド WSC-ST66M/TZ 10周年記念モデル(レジットデザイン)
近年広がりを見せるPEベイトフィネスに対応すべく作られた意欲作。スパイラルガイドによりPEラインのブランクスへの絡みや貼りつきを起きにくくしている。
上:ワイルドサイド WSS-ST 61UL/TZ 10周年記念モデル(レジットデザイン)
下:グラディエーター マキシマム GX-61LS マックスチェンジャー61L(レイドジャパン)
鬼形さんによると、ガイドセッティングはある程度は黄金比というのが決まっているが、そこから微妙に変更を加えることで、ロッドごとの個性や味付けの違いが生まれるという。
上:フリッピンスティックモデル775-2(フェンウィック)
下:ワイルドサイドWSC 76MH-T(レジットデザイン)
鬼形さんがどうしてもワイルドサイドのラインナップに入れたかったというフリッピングロッドは、1980年ごろに生産されたフリッピンスティックを参考に作られている。
ワイルドサイド WSC-G66ML(レジットデザイン)
温故知新。最新素材が最良とは限らないことを教えてくれる100%グラスのクランキングロッド。ワイルドサイドを代表する1本だ。
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2